日本橋はやし矯正歯科院長 林一夫です。
今回は私が発表した論文(Journal of Biomechanics 掲載論文)より3Dデジタル矯正に関するものをご紹介します。
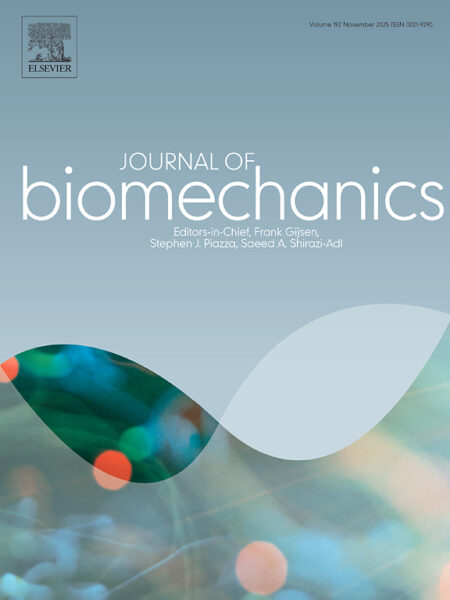 |
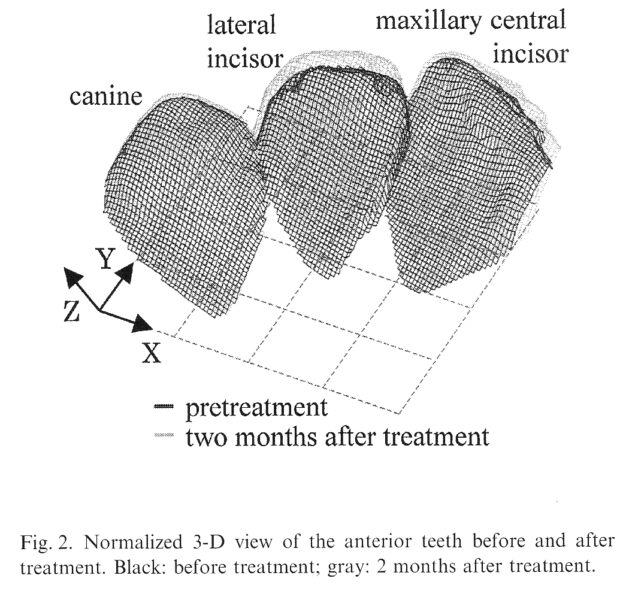 |
この研究の目的
今回の研究は「矯正治療で歯がどのように動いているのか」を、三次元的に正確にとらえる方法を開発することが目的でした。
従来の歯科矯正学では、歯の移動はレントゲンの二次元的な平面上でしか評価できず、「実際にどの方向へ、どの角度で動いているのか?」を定量的に把握することは困難でした。
そこで私は、「有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)」という物理学的な考え方を応用し、
歯の動きを3D空間内で正確に計測・可視化できるシステムを確立しました。
どんな方法で解析したのか
この研究では、3Dスキャナーを用いて治療中の歯列模型を高精度にデジタル化し、各歯の位置を三次元的に比較しました。
具体的なステップは次の通りです。
- スリットレーザーを用いた3Dスキャニングで歯列模型を測定
- 上顎第一大臼歯を基準点として自動的に位置合わせ
- 各歯の移動を「回転行列」と「並進ベクトル」で算出
- 「有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)」を導き、その軸まわりの回転と軸に沿った移動として歯の動きを表現
- 得られた結果を三次元のベクトルとして可視化
モデル症例
22歳男性(アングルⅢ級不正咬合、前歯部中等度叢生)を対象とし、マルチブラケット装置を用いた治療を実施。
印象採得※は、
- 装置装着前
- 装着直後
- 10日後
- 1か月後
- 2か月後
の5時点で行い、歯の移動軌跡を比較しました。
※「印象採得(いんしょうさいとく)」とは、歯や歯列、お口の中の正確な型を取る(型採りする)ことを指します。
今回の印象採得はシリコーン印象材を用い非常に高精度の歯列模型を作製しています。
結果と意義
この3D解析法により、歯の動きを単なる位置の変化ではなく、「回転」と「並進」として明確に表現できました。
例えば、ある歯が「どの方向に」「どれくらい回転しながら」「どれだけ動いたか」を視覚的に理解できるようになり、これまで「感覚」に頼っていた歯科治療の世界を、「感覚ではなく定量的な科学」に近づける一歩となりました。
この成果は、国際的な学術誌 Journal of Biomechanicsに掲載されました。
矯正分野の論文としては非常に稀なケースであり、またこの分野の研究を行っている医師・歯科医師の業績が同誌に採択された例はごくわずかです。
今の臨床への応用
この研究で確立した3D的な歯の動きの表現や理解のしかたは、現在の「デジタル矯正(SureSmile/3Dシミュレーション)」にも直結しています。
例えば、当院で導入している
- CBCTによる骨格評価
- 3Dスキャンによる歯列データ
- シュアスマイルによるバーチャル治療設計
これらの技術の根底には、「歯の動きを3D空間で正確に捉える」という、この研究の考え方が生きています。
論文情報
Title: A novel method for the three-dimensional (3-D) analysis of orthodontic tooth movement -Calculation of rotation about and translation along finite helical axis.
Author: Hayashi K, et al.
Journal: Journal of Biomechanics 2002 Jan;35(1):45-51. DOI: 10.1016/s0021-9290(01)00166-x
論文URL
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11747882/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002192900100166X?via%3Dihub
まとめ
- 歯の動きを三次元で解析する世界初の手法を開発
- 有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)を応用して、歯の回転と並進を定量化
- 国際誌 Journal of Biomechanics に掲載
- 現在のデジタル矯正技術の基盤に応用されている
院長からのコメントー感覚の技術から科学的に再現できる医療へー
この研究を通じて、矯正治療は“感覚の技術”から“科学的に再現できる医療”へ進化しました。今後も臨床の現場に、研究で得た知見を還元していきたいと思います。
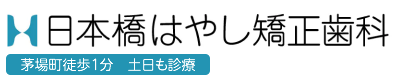
 0120-182-704
0120-182-704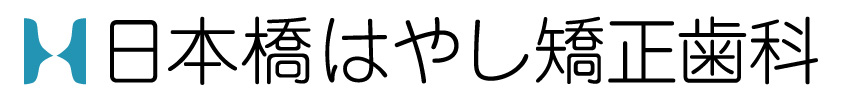


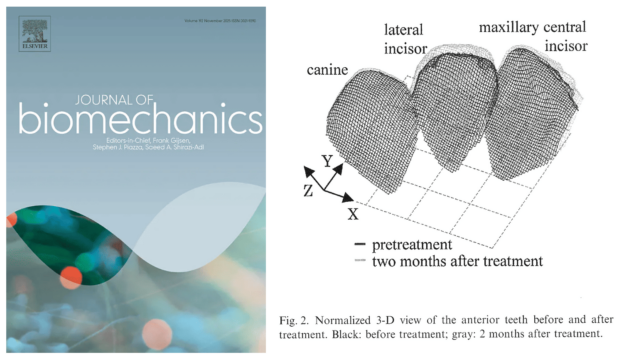
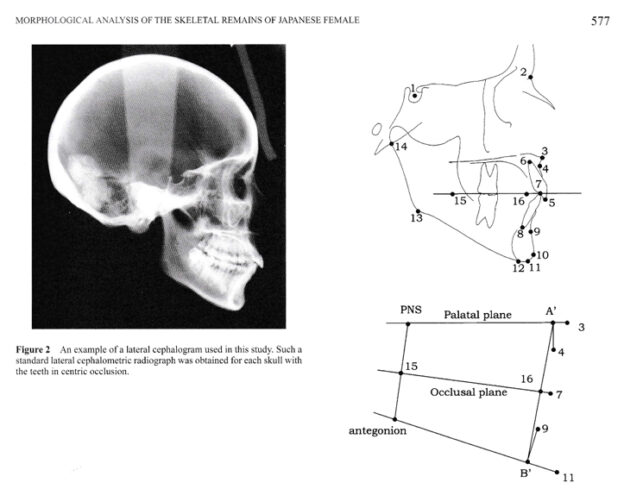
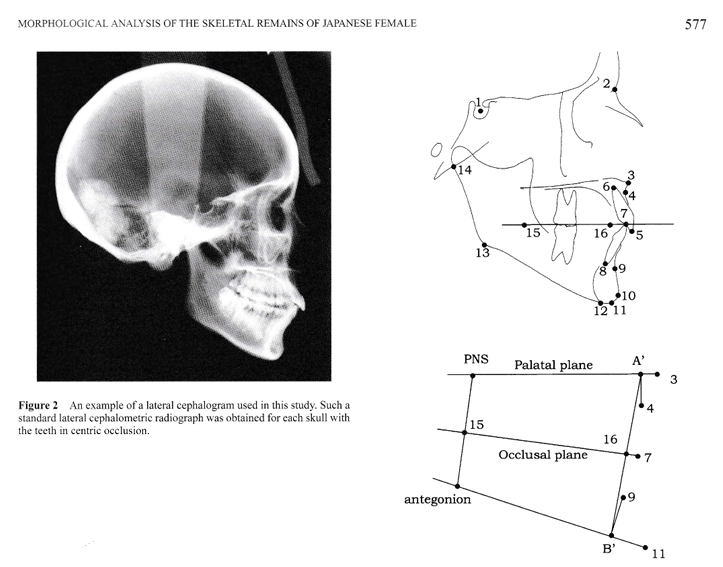
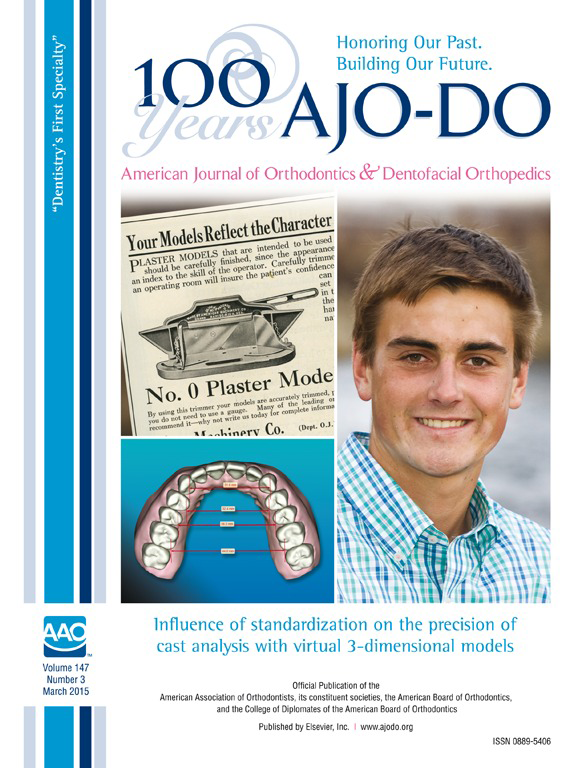
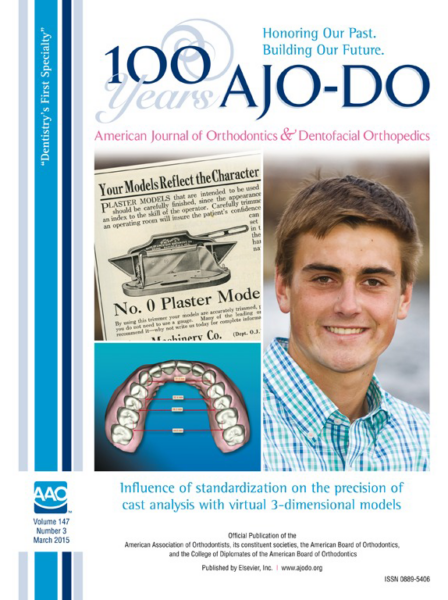
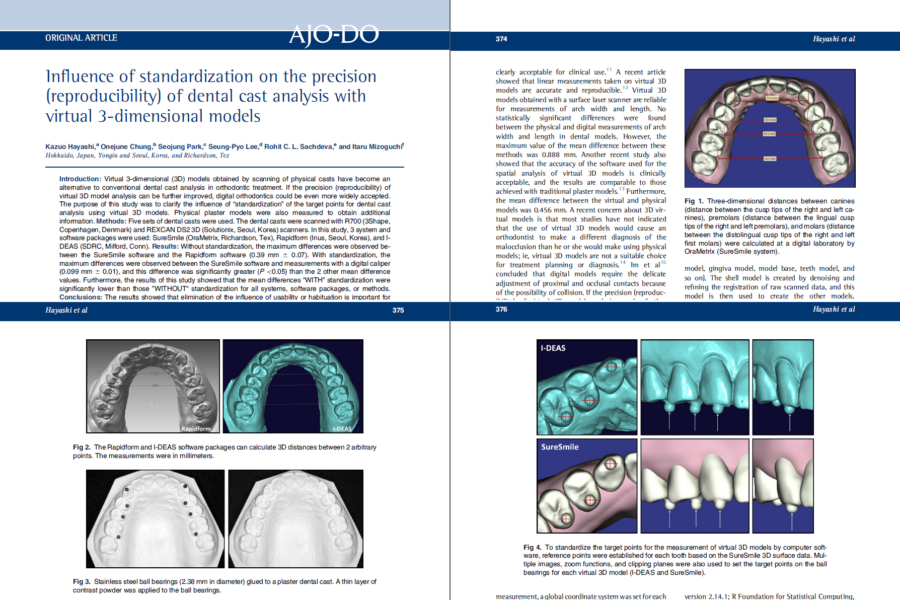

 0120-182-704
0120-182-704