みなさんこんにちは。日本橋はやし矯正歯科 院長の林 一夫です。
以前のコラムで、日本橋はやし矯正歯科では新しい外科的矯正治療 “サージェリーファースト・アプローチ (SFA)” に力を入れていることをお話しましたが、今回はその第二回目のコラムとして、多くの患者さまから質問を受けることがある外科手術について、より詳しくお話したいと思います。
▼こちらで詳しく説明しています
サージェリーファーストについて | 日本橋はやし矯正歯科
▼第一回目のコラムも併せてご覧下さい
サージェリーファースト・アプローチに力を入れています
日本で多いサージェリーファースト・アプローチの患者さまタイプ
日本人の患者さまのサージェリーファースト・アプローチでは、下顎前突(下顎の骨が前方に突出している状態)の治療を行うことが比較的多く、私のクリニックでも下顎前突の患者様が一番多くいらっしゃいます。
また比較的軽度の顔面非対称(正面から見てあごが左右どちらかに曲がっており、顔が歪んでいる状態)の場合は、下顎前突と同様に下あごの外科手術のみで治療を行うことが可能な場合があります。
このような場合、従来の手法では手術後の入院が必要でしたが、それが患者さまにとって、治療への大きなハードルとなっていました。
外科手術に踏み切れない様々なハードル
ところが、これまでの外科的矯正治療には様々なハードルがあり、外科手術に踏み切れない患者さまも数多くいらっしゃいました。
1週間ほどにわたる入院期間
入院期間は1週間程度を要することが多いので、お仕事が忙しい方はなかなか外科手術を行う決断が出来ないことがあります。
口を開けられない不便さ
また、外科術後に顎間固定といって上顎と下顎を完全に固定し、一定期間口があけられない状態が続くため、手術を躊躇される患者さまもいらっしゃいます。
術後の「腫れ」の可能性
さらに、手術後にアゴの周辺が長期間腫れてしまうことも少なくなく、人前に出ることがはばかられてしまう方もいらっしゃいます。
このような問題をできるだけ解決し、より多くの方に必要とされる手術を受けて頂けるようにしました。
入院が不要の “Day Surgery”
日本橋はやし矯正歯科では、リラ・クラニオフェイシャル・クリニックと提携し、前述した問題点を解決できるサージェリーファースト・アプローチによる治療を積極的に行っています。
まず下顎のみの外科手術であれば、入院を必要としない “Day Surgery” を行っています。つまり日帰りでの外科手術ということです。
手術後、回復室で4-5時間経過を観察し、問題がなければそのまま帰宅することが可能です。
リラ・クラニオフェイシャル・クリニックのサイトも併せてご覧ください。
写真は、リラ・クラニオフェイシャル・クリニックの手術室と回復室です。
▼こちらが手術室です。

▼術後に安静にして頂くための回復室がこちらです。

口を動かせるから安心です
また、上あごと下あごを口が開かないように完全に固定してしまう顎間固定は行いません。新しい技術を用いて手術で動かした顎の骨同士をプレートでしっかり固定できます。
輪ゴムなどで弱い力をかけながら骨の位置関係を保つように処置することはありますが、顎間固定することはありません。
24時間が経過した以降には顎を動かすことが可能となり、食事もやわらかいものであれば通常どおり行うことが可能です。
術後の「腫れ」を防ぎます
さらに、この顎を動かすということが術後の腫れを抑える事にとても有効に働きます。また腫れを積極的に抑える処置も併用しますので、術後の腫れもかなり軽減することが可能になっています。
お仕事への支障も最低限になります
患者さまの中には、金曜日に手術を行い、土曜日と日曜日を回復期間に当て、月曜日から出勤される方もいらっしゃいます。
マスク等を着用すれば問題なく出勤できることがほとんどですし、普通に会話もして頂けますので、お仕事に大きな支障はありません。
このように、日本橋はやし矯正歯科では、サージェリーファースト・アプローチを用いた外科手術後の患者様の負担を、可能な限り軽減する努力を行っております。
また術後の矯正治療も、デジタル矯正により治療期間の大幅な短縮が可能になっています。
今まで、外科手術を受けるかどうか悩んできた皆さまに最良の治療を提供できる環境が整っております。どうぞ一度、カウンセリングをお受けいただければと思います。
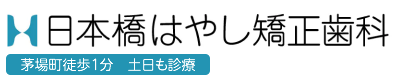
 0120-182-704
0120-182-704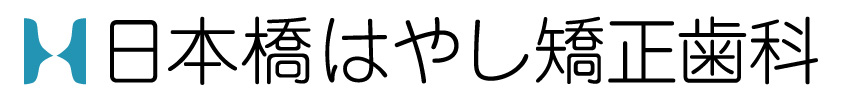












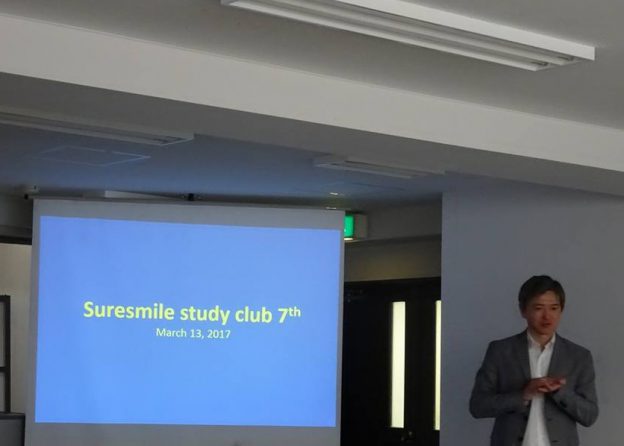

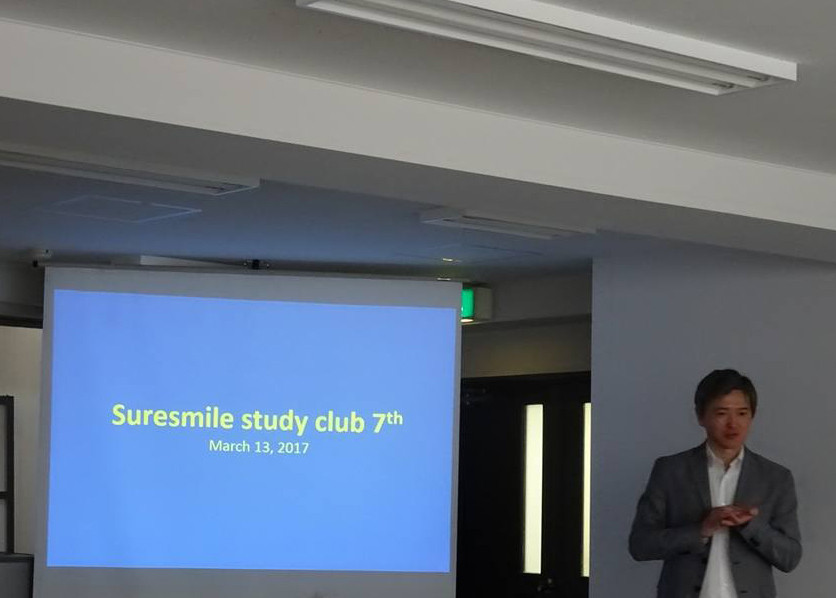
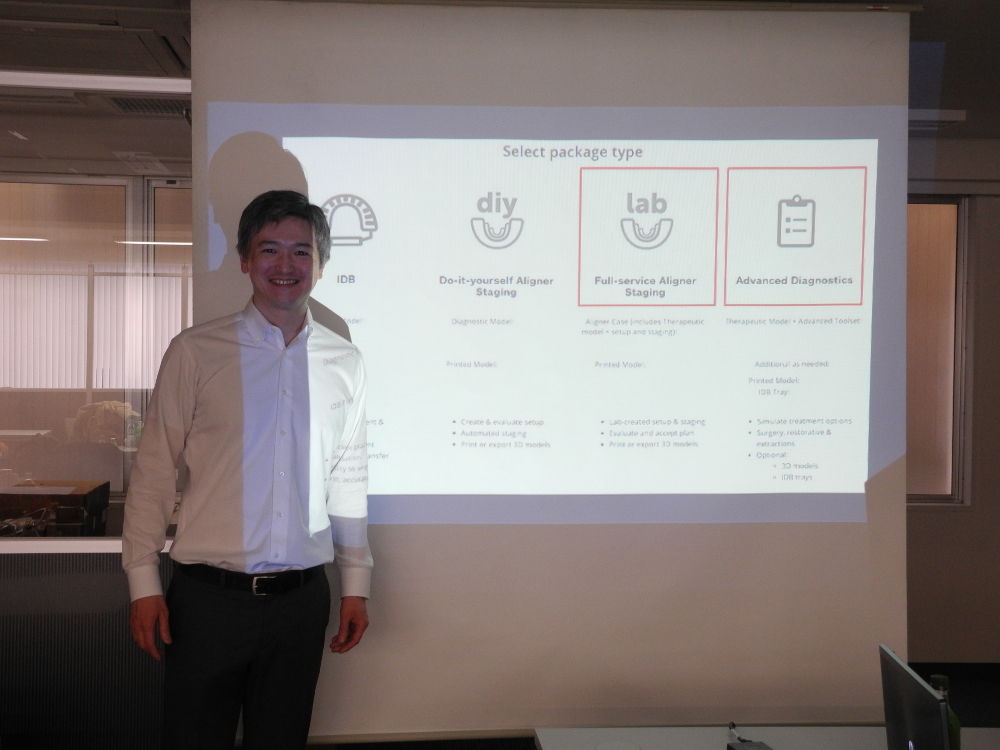
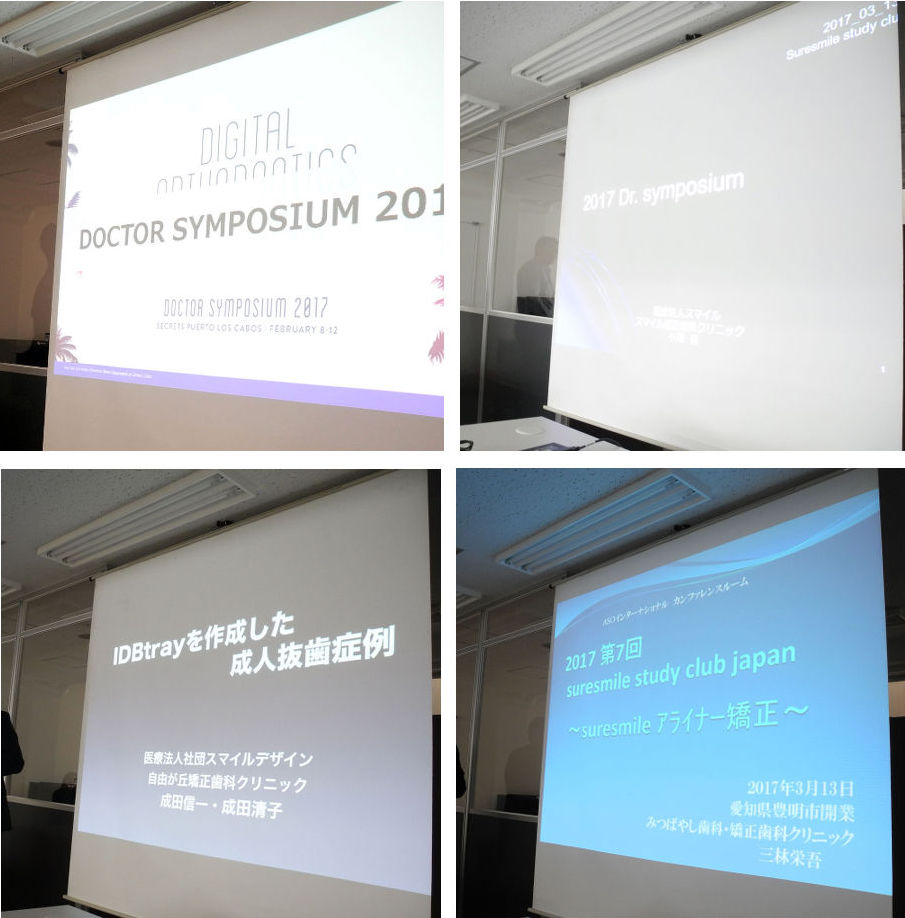


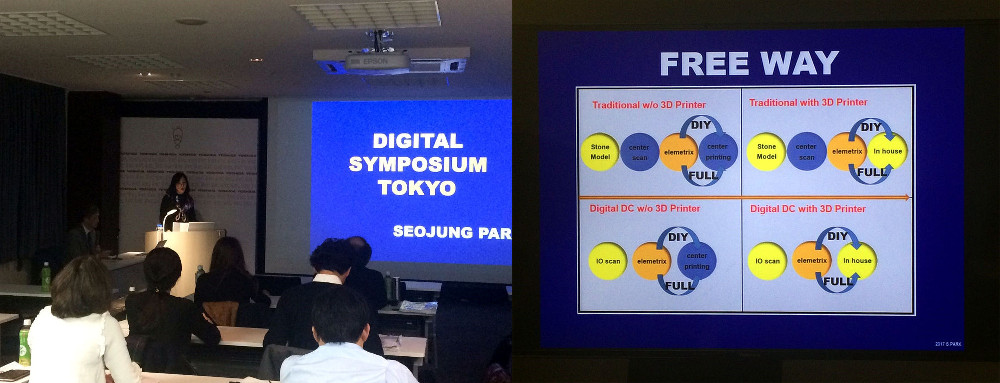





 0120-182-704
0120-182-704