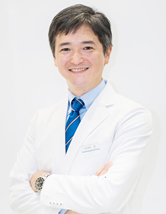
日本橋はやし矯正歯科 院長 林 一夫
資格 (ドクターの紹介はこちら)
・日本矯正歯科学会認定医
・日本矯正歯科学会指導医
・日本顎関節学会専門医
・日本顎関節学会指導医
・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター
日本橋はやし矯正歯科 TOP > コラム > 口唇閉鎖不全(ポカン口)はデメリットだらけ?治療法と事例を紹介
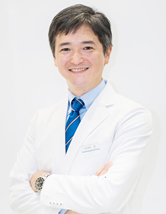
資格 (ドクターの紹介はこちら)
・日本矯正歯科学会認定医
・日本矯正歯科学会指導医
・日本顎関節学会専門医
・日本顎関節学会指導医
・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター

いつも口が開いている状態である口唇閉鎖不全(ポカン口)は、放置しておくと口呼吸の習慣が定着するなどして様々なデメリットが生じ、日常生活に支障をきたしかねません。
この記事では口唇閉鎖不全になる原因や、放置した場合のリスクについて説明した後、口唇閉鎖不全を改善するための治療方法をご紹介します。既に口唇閉鎖不全だと判明している方はぜひ参考にしてください。
目次
口唇閉鎖不全(ポカン口)とは、その名の通り日常的に口が開いてしまっている状態です。食べたり話したりといった、口の基本的な機能が通常どおりに発達していない状態を言います。
口唇閉鎖不全になっているか判断するにあたり、以下のようなチェック項目があります。
咀嚼に問題があり、またそれ以外の項目に関して1つでも当てはまっている場合は、口唇閉鎖不全や口腔機能がしっかり発達していない可能性が高いです。
口唇閉鎖不全になってしまうのには、以下のような原因があります。
口の筋肉の発達が不十分なことにより、口唇閉鎖不全に陥るケースが多いです。その他、歯並びが悪かったり、舌小帯が短いために舌の動きが制限されたりといったことも原因となります。また、低位舌(舌の筋肉が十分に発達せず、下側の歯についてしまう)ことも口唇閉鎖不全を引き起こすことがあります。
アレルギー性鼻炎や鼻中隔湾曲症といった鼻の病気が重度な場合でも、口唇閉鎖不全になることがあります。
口や鼻以外で、例えば肥満といった原因が挙げられます。
口唇閉鎖不全の原因はさまざまです。

口唇閉鎖不全には、様々なデメリットがあります。まず口呼吸になってしまうことから、集中力が低下したり、鼻閉、気道閉塞、いびきなどの症状が発生したりする可能性があります。
また、喉や扁桃周辺が乾燥するため細菌の働きが活発となり、アレルギー疾患が出る場合もあるのです。
さらに口呼吸は鼻呼吸と比べてウイルスを取り込みやすい呼吸法であるため、風邪やインフルエンザにも感染しやすくなります。
口唇閉鎖不全は口呼吸の他、食生活の偏りをもたらすこともあります。
その蓄積が将来メタボリックシンドロームといった生活習慣病を引き起こす可能性があります。
口唇閉鎖不全を放置していると、梅干状隆起が発現するというリスクがあります。
口元が出ていることを気にして、無理矢理口を閉じようとすることで、オトガイ部(下顎の前面)に膨らみができてしまうというものです。
この梅干状隆起によって、口元が出ている状態がより顕著になり、見た目の問題からコンプレックスを抱えるケースも多いです。
また口唇閉鎖不全の放置により、先ほど解説したデメリットが実際に生じる可能性がどんどん高まります。
そうなれば、単に見た目の問題だけで済まされず、あらゆる症状が出ることで日常生活に支障をきたしかねません。
こうしたことから口唇閉鎖不全はいつまでも放置せず、なるべく早期に改善しておくことが望ましいのです。
口唇閉鎖不全の場合、アレルギー性鼻炎のような鼻の疾患がなく鼻呼吸ができたとしても、口がずっと開いていることから口呼吸になりやすいです。
こうした口唇閉鎖不全と口呼吸の関連性について、研究により以下のようなことがわかっています。( https://www.jstage.jst.go.jp/article/kds/60/1/60_KJ00004719264/_article/-char/ja/)[※]
鼻を閉じた状態で口を開ける時、口唇閉鎖不全でない人はオトガイ筋(下顎の前面にある表情筋)がよく働いていたのに対し、口唇閉鎖不全の人は舌周辺の筋肉の働きが弱い
口唇閉鎖不全の人は、鼻を閉じた状態では咀嚼時間が短くなった
鼻を閉じた状態で咀嚼する際、口唇閉鎖不全でない人は口が開いた時に舌周辺の筋肉が最もよく働くのに対し、口唇閉鎖不全の人は口を閉じようとする時にオトガイ筋が最もよく働いた
※出典:口唇閉鎖機能と口呼吸の関連性|九州歯科学会雑誌
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kds/60/1/60_KJ00004719264/_article/-char/ja/
口呼吸になると以下のような様々なデメリットが生じてしまいます。
唾液の分泌量が減るため、口の中が乾燥状態となって様々な細菌が増殖します。こうした細菌が原因で、口臭が悪化してしまうのです。
口呼吸になることで、風邪やインフルエンザの原因となるウイルスが体内に入りやすくなるため、その分発症しやすくなります。
喉や扁桃周辺が常に乾燥した状態になることで細菌が増殖し、扁桃肥大が引き起こされたり、アレルギー疾患にかかったりします。
口を閉じるための力と舌の圧力との間に不均衡が生じることで、上顎前突や開咬といった噛み合わせの異常が発生する場合があります。
口唇閉鎖不全やそれに伴う口呼吸を放置してしまうと、様々なデメリットが生じかねません。そのため、早期に口唇閉鎖不全を改善しておくことが重要です。
口唇閉鎖不全の治療方法は、一般的に以下のような手順をとります。
1. 口元が出ている状態を改善するうえで邪魔となっている歯を抜く
2. 抜歯したところのスペースを利用し、前歯を奥に移動させる矯正治療を行う
場合によっては虫歯などない健康な歯を抜かざるを得ない場合もあり、実際に治療を受ける際には精神面での準備が必要です。
ここでは口唇閉鎖不全の実際の治療事例を紹介します。



口が閉じにくく、無理に閉じようとするとオトガイ部に“しわ”ができてしまっている状態です。
専門的には上下顎前歯の唇側傾斜により、口唇閉鎖不全の状態になっています。
このような場合は口呼吸を伴っていることが多く、お口の周りの筋肉のバランスが悪くなり、より症状が悪化することが知られています。
矯正治療によって見た目だけではなく、機能的に健康な状態に改善することが必要となります。
この場合、矯正用のインプラント(アンカースクリューともいいます)を用いて、抜いた隙間を全て使って前歯を後退させます。装置は、裏側矯正を選択されました。



治療期間は2年3か月でした。
矯正用のインプラント(ミニスクリュー)を用いることにより、上下の前歯を可能な限り後退させることができましたので、比較的短い治療期間でとても良い治療結果を得ることができました。
口唇閉鎖不全(ポカン口)は、口呼吸を引き起こします。口唇閉鎖不全や口呼吸の状態を放置してしまうと、感染症や口臭悪化、生活習慣病など様々なデメリットが生じかねません。
口唇閉鎖不全は抜歯や歯列矯正によって治療することができます。
日本橋はやし矯正歯科では最新のデジタル矯正治療で最適な治療方法をご提案しておりますので、是非1度カウンセリングをお受けください。
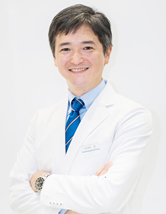
資格 (ドクターの紹介はこちら)
・日本矯正歯科学会認定医
・日本矯正歯科学会指導医
・日本顎関節学会専門医
・日本顎関節学会指導医
・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター
| 1995年 | 北海道医療大学歯学部卒業 |
|---|---|
| 1999年 | 北海道医療大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了・学位取得 |
| 1999年 | 海道医療大学歯学部矯正歯科学講座 助手 |
| 2003年 | アメリカ・ミネソタ大学歯学部口腔科学科 客員研究員 |
| 2006年 | 北海道医療大学歯学部矯正歯科学講座 講師 |
| 2007年 | 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野 講師 |
| 2007年 | 北海道矯正歯科学会 理事 |
| 2008年 | アメリカ・ノースカロライナ大学歯学部矯正科 客員教授 |
| 2008年 | 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野 准教授 |
| 2011年 | Digital Orthodontics 研究会 副会長 |
| 2015年 | 日本橋はやし矯正歯科 開院 |
| 2018年 | K Braces矯正歯科原宿駅前 総院長就任 |
| 2021年 | 日本デジタル矯正歯科学会 副会長就任 |
| 2002年 11月 | 日本矯正歯科学会認定医(第2293号) |
| 2007年 8月 | 日本矯正歯科学会指導医(第608号) |
| 2013年 5月 | 日本顎関節学会専門医(第343号) |
| 2013年 5月 | 日本顎関節学会指導医(第208号) |